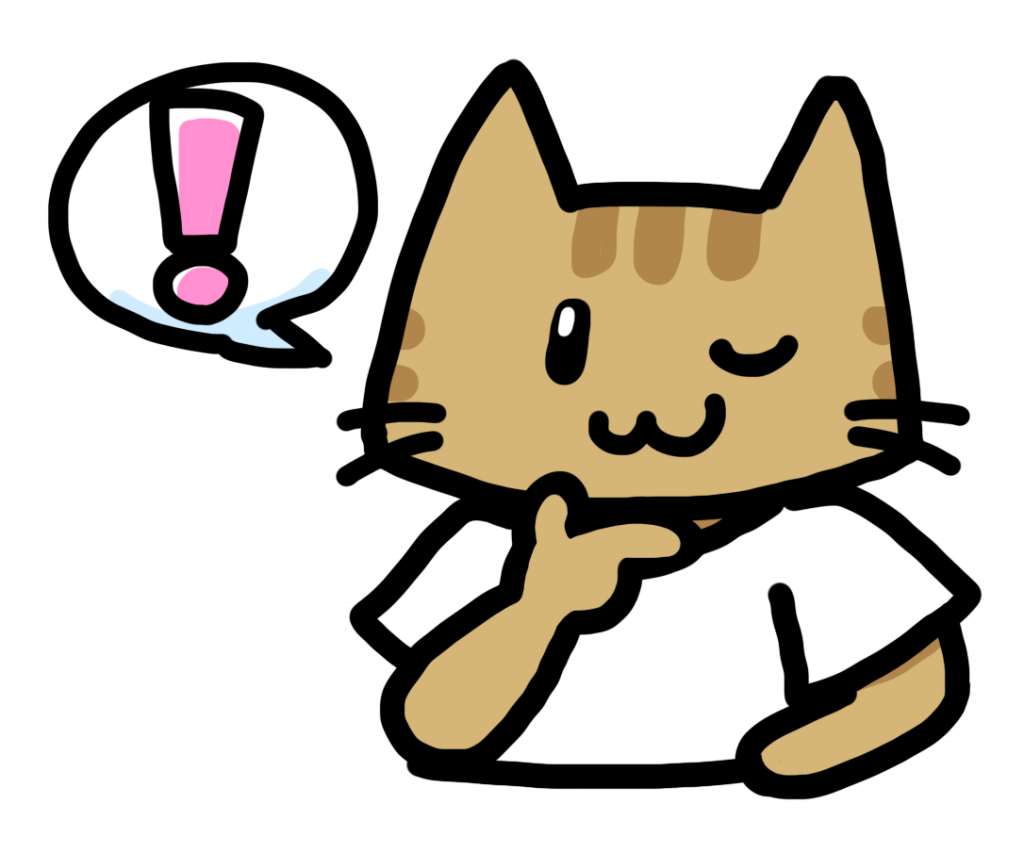みなさん、こんにちは!今日は大学進学の準備に役立つ話題をご紹介します。高校生活で最初に受ける1学期の定期考査、これが大学進学に向けた最初の重要なステップとなります。特に注目すべきは数学Ⅰの試験で、範囲は「数と式」から「二次関数」までです。
驚くことに、この試験でのパフォーマンスは、大学選びから進学方法まで大きく左右します。さて、なぜ数学Ⅰがこんなにも重要なのか、一緒に探ってみましょう!
新しいことを学ぶ際、その新たな知識だけが必要なわけではありません。基礎となる知識と新しい知識が関連付けられることで、全体の理解が進むのです。たとえば、整数のたし算やひき算ができなければ、どんなに分数の勉強を頑張っても理解は難しいですよね?
それと同じように、高校数学の基礎となるのが「数学Ⅰの二次関数までの内容」です。この部分がしっかり理解できていないと、数学Ⅱ・BやⅢの学習は難しくなり、成績が下がってしまう恐れがあります。
ここで一つ、「文系だから数学は要らない」と思っている方もいるかもしれませんね。でも、それはちょっと待ってください。文系の生徒さんでも、数学を理解しておくことにはたくさんのメリットがあります。
数学が苦手だからといって、「国立大学は無理だから私立に行こう」と決めつけていませんか?でも、高1から地道に数学を学んでいれば、私立だけでなく国立大学も十分に選択肢に入れられますよ。
また、今の私立大学入試では、推薦・総合型選抜で合格する人が全体の50%を超えているという現実があります。つまり、面接での合格者が学力試験で合格する人より多いんです。
だからこそ、数学Ⅰを完璧に理解し、その流れで数学Ⅱ・BやⅢでも高得点を維持することが、数多くいるライバルたちとの勝負で打ち勝つ秘訣です。
要するに、大学受験の第一歩は数学Ⅰの二次関数までの内容を完全に理解することから始まるのです。それが大学進学の道を開く最初の一歩となるでしょう。それでは皆さん、一緒に数学の勉強を始めましょう!