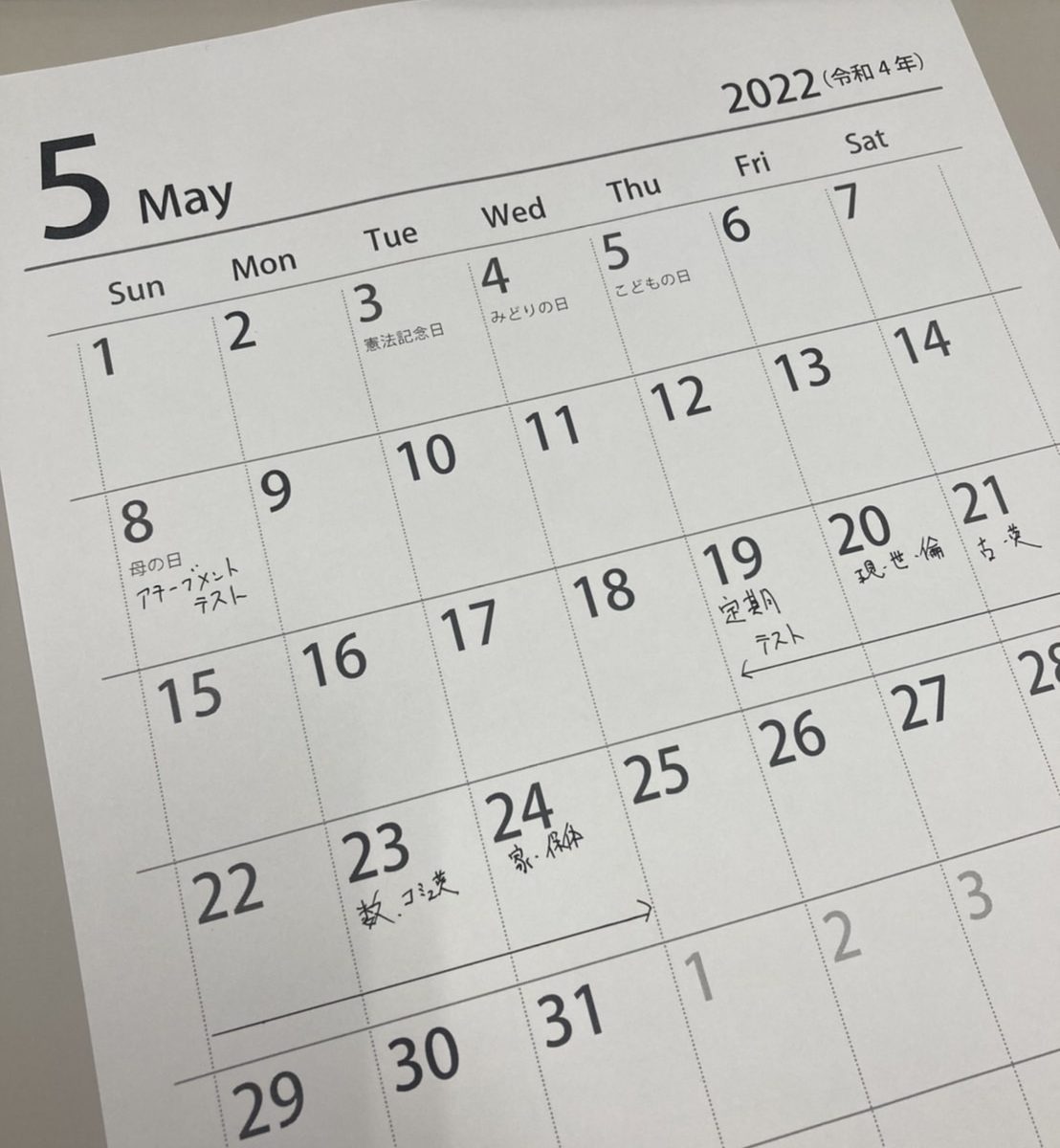梅雨入りして、雨の日が増えましたね。
雨が降っていなくても、なんだかすっきりしない日が多い気がします。
天候や気圧の変化、確かにしんどいときありますよね…。
こんなときは誰もがモチベーションが落ちてしまうものです。
受験生にとっても影響があるようで、この6月は勉強時間や勉強量が減ってしまうというデータが出ているそうです。
どうせ雨だし…授業もないし今日は自習室に行くのはやめよう、この復習は後回しにしよう、とか。
結局は勉強に集中して取り組めない現象が起きやすくなるようです。
そんなときに、「いつものルーティン」を決めておくと、いちいちその日の天気やモチベーションに左右されずに勉強に集中できます。
思うように動けないとき、目の前のことをコツコツと。
などとよく言いますが、これはこの「いつものルーティン」をまずやることだと思います。
いつものことが出来ると、気が付くといつもの気持ちに戻ってるなぁと思うことがよくあります。私もあります。
そうやって気持ちを元に戻してくれるのが「いつものルーティン」なので、勉強においても絶対に習慣付けたほうがいいと思います。
あと、6月は実はチャンスだということ。
多くの受験生の勉強量が減ってしまうこの時期こそ、ライバルに差をつけられるチャンス!
もちろんこのあとにやってくる夏が受験の天王山と言われる大事なものではありますが、
夏は現役生も比較的時間に余裕があるのでギアを上げてくるだろうし、部活を引退した人も本腰を入れてくることを考えると…かなりの接戦ですよね。
となると、夏の前のこの今こそが、一歩リードできるチャンスであると言えますね!
一喜一憂してしまう梅雨時期ですが、いつものルーティンをこなしていいリズムを掴んでくださいね。
先日、小学1年生になったばかりの姪っ子が、『あたし、るーちんあるもん』と言ってました笑
そんな言葉もう知ってるのー?と思わず大笑いしてしまいました。
でもよく聞いてみると、明日着ていく服と習い事の支度を寝る前にしっかり自分で準備しているようですよ~!
凄いなぁ~と感心しました(^^)
ではまた。