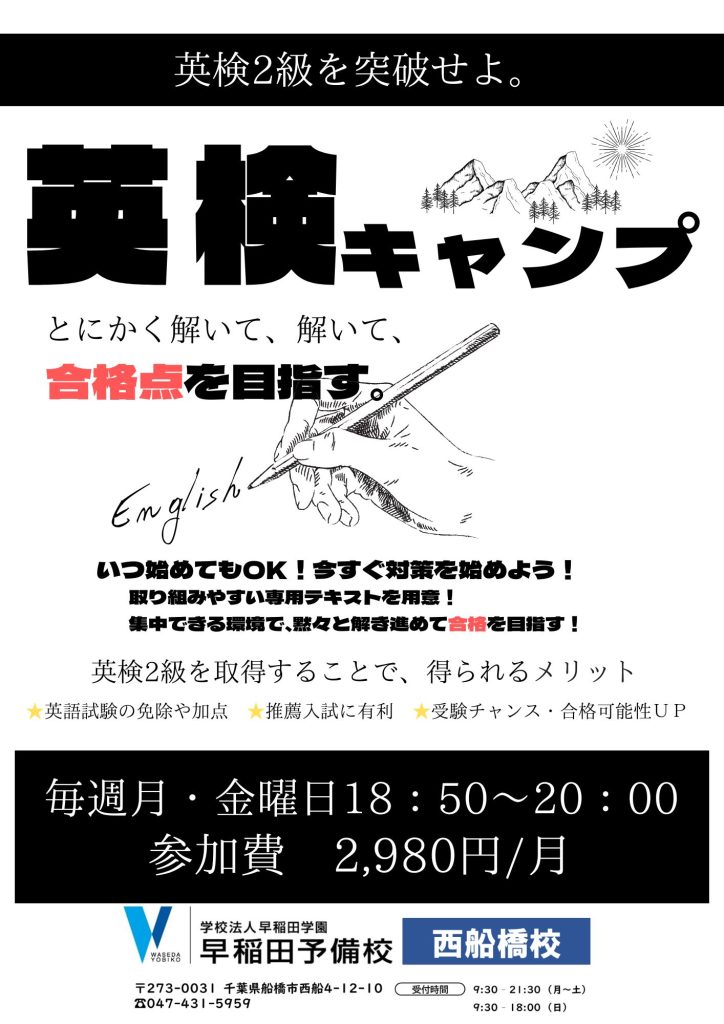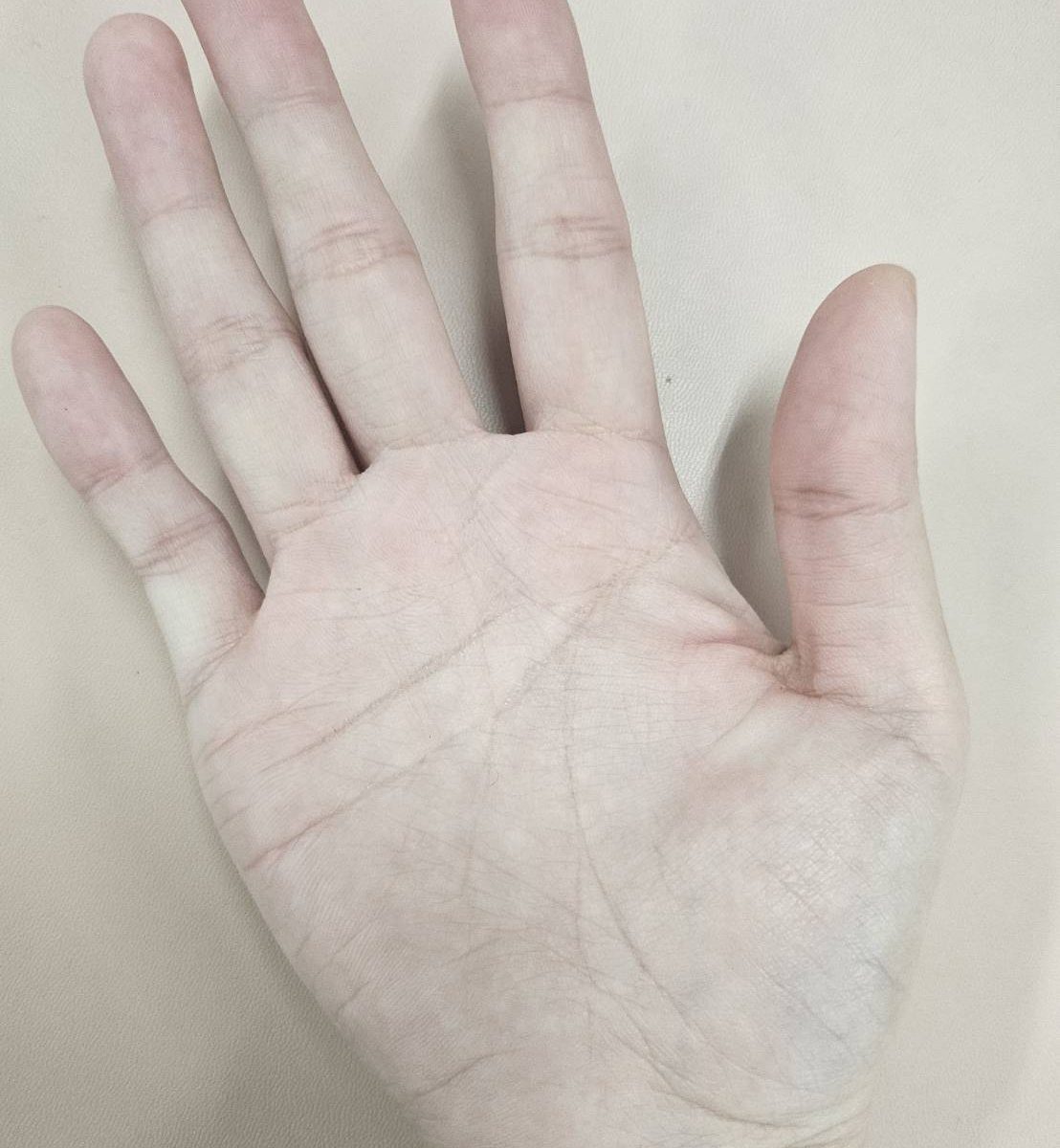高3生・卒生はいよいよラストスパートの時期ですね。
最後までサポートします。安心して戦ってきてください。
そして高1・高2生の皆さんへ。難関大に合格した先輩は、高1・高2のうちから受験を意識した勉強を始めています。
受験勉強は高3から一気に…と思われがちですが、早い時期に基礎を固めた生徒ほど受験学年で飛躍的に伸びます。
特に英語は、単語・文法・リスニングなど積み上げが必要で、短期間では仕上げにくい科目です。
新学年が始まる前から準備を始めて、良いスタートを切りましょう!
✨新学期準備 特別講習のご案内✨
新学年に向けて「新学期準備講座・特別講習」を開講します。万全の状態で新学年を迎えましょう!
■リスニング対策講座(高1・高2)
【日程】2/6・13・20・27(金)18:50~20:00
リスニング対策、後回しになっていませんか?
共通テストや英検に向けて重要な分野ですが、日頃からしっかり対策できている生徒は実は多くありません。「センスが必要」「たくさん聞いて耳を慣らさないと無理」と思われがちで、つい優先順位が下がってしまうからです。
しかし入試は、たった1点で合否が分かれます。
「やれば取れる点」を後回しにするのは、正直もったいない。
本講座では「リスニングはスキルではなく知識」という視点から、単語・文法・発音を整理し、なんとなく聞く勉強を卒業して得点につながる聞き方を身につけます。
■新高3英文法・特別復習講座(高2)
【日程】2/12・26(木)18:50~20:00
英文法、「分かったつもり」になっていませんか?
高2で学んだ内容は一度理解していても、時間が経つと抜け落ちやすい分野です。
そして入試の長文問題は、文法の土台があるかどうかで読み取りの正確さが大きく変わります。
高3に進む前の今こそ、「高2英文法」講師のもとで重要事項を総復習し、受験に向けた土台を固めましょう。
🌸新学期準備講座・春期講習🌸
3月2日から新学期準備講座、3月21日から春期講習が開講します。
受験で使用する科目は、ぜひこの機会にしっかり受講しておきましょう!
おすすめの講座は、新学年に向けた生徒面談の際にご案内いたします。
これから勉強を本格的に始める生徒にも取り組みやすい内容になっておりますので、
「勉強を頑張りたいけど何から始めればいいか迷っている友人」
「塾・予備校を探している友人」
がいましたら、ぜひ早稲田予備校をご紹介ください!